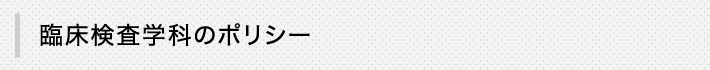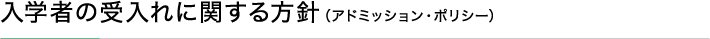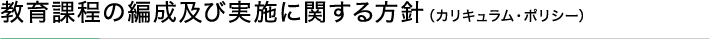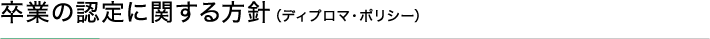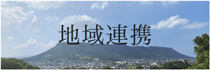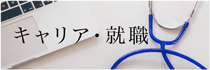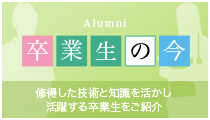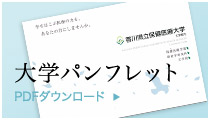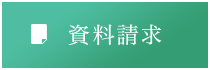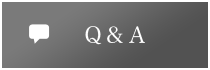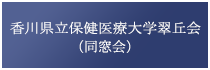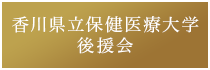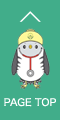- 論理的思考に必要な基礎学力を有している人
- 責任感と協調性があり、主体的に行動できる人
- 知的好奇心が旺盛で、科学的な観察力を持つ人
- 臨床検査技術を基盤に、地域の多様な分野で活躍したい人
臨床検査学科では、デイプロマ・ポリシーの実現を目指して、以下の方針(考え方)でカリキュラムを編成する。
進級に関しては、各学年で定められた単位を修得する必要がある「進級制」を採用する。
-
臨床検査学学修の効率化を目指して、基礎科目群から臨床検査専門科目群へと積み上がる科目構成とするとともに、臨床検査に関連する領域の学修も含め、社会において幅広く活躍できる能力も培える科目配置とする。全科目は、[基礎科目群]と[臨床検査専門科目群]に大きく区分する。
[基礎科目群]は、<人文科学>、<社会科学>、<自然科学>、<外国語>、<情報科学>、<健康科学>、<総合科目>及び<専門基礎>に細区分する。
[臨床検査専門科目群]は<分析検査学>、<形態検査学>、<検査情報解析検査学>、<総合検査学>、<臨地実習>に細区分している。 -
基礎科目群として、高い倫理観をもつ豊かな人間性を養うために哲学、倫理学などの人文科学系科目と、社会学、経済学などの社会科学系科目を配置し、さらに高等学校での学習内容を確認し、専門領域への橋渡しとする目的で、物理学、化学、生物学などの自然科学系科目と生理学、生化学などの専門基礎科目を配置する。
また、情報化社会への対応のために検査データ管理に必要な情報科学を配置した。国際的視野を持って活動できる人材育成のため、英語と中国語を配置しており、特に、英語学習では、基礎英語、英会話、医療英語、文献などの読解力を養う。専門基礎科目は、健康、疾病、病態を広く理解するとともに、人体の構造と機能を系統的に理解し、臨床検査についての専門知識、技術、医療チームとしての役割、他職種との連携を学修する目的で科目を構成する。また、国際的視野を広げるために国際保健論を設け、他職種との連携能力を修得するために、組織論と地域チーム医療論を配置している。 - 臨床検査専門科目群は、専門的知識・技術、科学的思考と研究能力を修得するため、検査結果や実験結果を総合的・多角的に判断分析、管理運営する基礎的能力及び検査技術を修得する目的で科目構成する。早期に学習への興味やモチベーションを高めるため、検査学概論、臨床検査体験実習、臨床医学Ⅰなどの科目を配置している。医療の高度化や安全管理・社会環境の変化に対応すべく、検診検査学、生殖補助医療技術論、リスクマネジメント、健康食品学などの科目も履修可能で、臨床検査技師の業務範囲の拡大内容についても修得できるように、医療安全管理学を中心に学内実習・演習を充実させている。臨地実習前には、臨地実習到達度評価を実施し、実習に必要な知識、技能や接遇能力を習得しているかの確認を行う。臨地実習は、臨地実習ガイドラインをもとに、実習施設との綿密なプログラム確認を行うことにより、総合的実践能力を高められる内容の科目編成とする。さらに、卒業研究は、少人数制で実施することで、科学的思考力、研究能力、及びデータ管理能力が高められる指導を行う。所定科目履修者は在学中に、健康食品管理士、遺伝子分析科学認定士及び食品衛生管理者・監視員の資格取得が可能な科目体制を設けている。
臨床検査学科では、以下に示された能力を卒業までに修得することを重視して成績評価を行い、所定の単位を修得した学生に対して、卒業を認め、学士(臨床検査学)の学位を授与する。
- 豊かな人間性と高い倫理観を身に付けている。
- 臨床検査に必要な専門的な知識・技術と実践能力を身に付けている。
- 臨床検査学発展のために、自らの能力の向上に努め、データ管理力や科学的思考力を用いて研究できる基礎的能力を身に付けている。
- 国際感覚を備え、臨床検査を通して、地域社会に広く貢献できる能力を身に付けている。
- 医療・環境・食品・保健分野などで、他職種と連携しながら、幅広く活躍できる能力を身に付けている。